\今話題の商品をランキングでチェック/
国民年金の免除後に支払いを再開したくなったら?追納制度のポイントを徹底解説
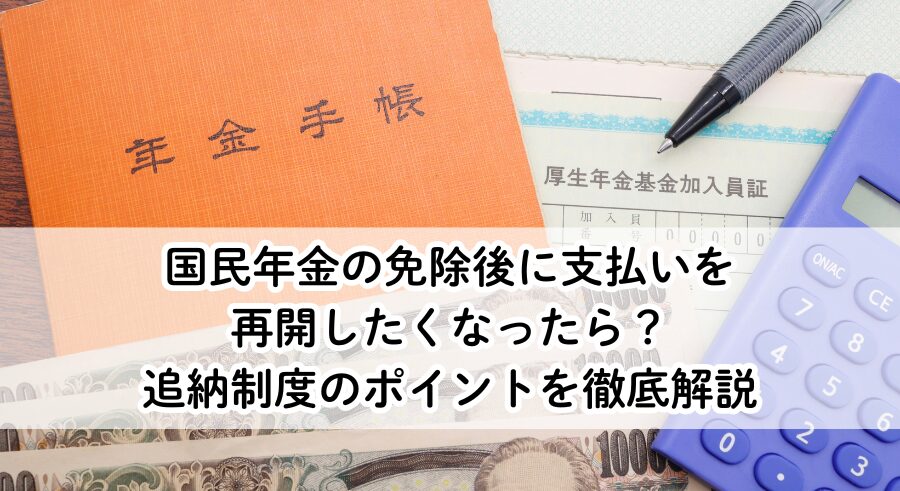
国民年金の免除後に支払いを再開したくなったら?追納制度のポイントを徹底解説
このような経験を持つ方は少なくないかもしれません。
そして、経済的に余裕ができた今、「過去の分を支払って、将来もらえる年金額を増やしたい」と考えることもあるでしょう。
その願いをかなえる制度が「追納制度」です。
ただ、追納と一言で言っても、「いつまで遡って払えるの?」「支払う金額は当時と同じ?」といった疑問が浮かびますよね。
この記事では、国民年金の追納制度の基本的な仕組みから、具体的な手続き方法、そして知っておきたいメリットや注意点まで、分かりやすく解説していきます。
あなたの将来の安心のために、追納制度について正しく理解し、ご自身の状況に合った選択をするための一助となれば幸いです。
過去の未払い期間を価値ある未来の資産に変える方法を、一緒に見ていきましょう。
追納制度とは?基本の仕組みと対象者

国民年金免除・猶予との違い
まず、国民年金の「免除」や「猶予」制度についておさらいしておきましょう。
これは、収入の減少や失業など、経済的な理由で保険料を納めることが難しい場合に、申請することで支払いが免除されたり、待ってもらえたりする制度です。
この免除や猶予を受けた期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」には含まれます。
しかし、保険料を支払っていないため、将来受け取る老齢基礎年金の金額には反映されません。
一方で「追納」は、この免除・猶予を受けた期間の保険料を後から支払うことで、年金の受給額を満額に近づけるための制度です。
つまり、免除や猶予は「将来の年金受給権を確保しつつ、支払いを待ってもらう状態」であり、追納は「その期間を、きちんと保険料を支払った期間として復活させる手続き」という違いがあります。
追納できる条件
追納制度を利用できるのは、特定の条件を満たした方に限られます。
その最も基本的な条件は、「国民年金保険料の免除、または納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある」ことです。
つまり、過去に正規の手続きを踏んで、日本年金機構から免除や猶予の承認を得ている必要があります。
単に保険料を支払わずに未納状態にしていた期間は、追納の対象にはなりませんので注意が必要です。
また、追納を行うためには、当然ながら国民年金の被保険者であることが前提となります。
例えば、会社員になって厚生年金に加入している方でも、それ以前に国民年金の免除を受けていた期間があれば、その分を追納することが可能です。
自分の年金記録を確認し、免除や猶予の期間があるかどうかを把握することが第一歩と言えるでしょう。
対象期間と適用されるケース
追納が適用されるのは、前述の通り、正式に「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の承認を受けた期間です。
具体的に、どのようなケースが考えられるでしょうか。
例えば、大学や専門学校に通っていた20歳以上の学生時代に「学生納付特例」を利用していたケースは非常に多いです。
また、退職や失業により一時的に収入が途絶え、「全額免除」や「一部免除」の申請をしていた期間も対象となります。
その他にも、所得が一定基準以下であるために「納付猶予制度(50歳未満が対象)」を利用していたフリーターや非正規雇用の方の期間なども考えられます。
これらの期間は、将来の年金額には反映されていません。
その後、就職して収入が安定したり、経済的な余裕が生まれたりした際に、この追納制度を活用することで、将来の安心を自ら積み立てていくことが可能になるのです。
追納できる期間と期限切れの影響

原則10年以内
追納を検討する上で最も重要なルールの一つが、支払い可能な期間に限りがあることです。
具体的には、追納ができるのは「追納の申し込みをする月から遡って10年以内」の免除・猶予期間に限られます。
これは法律で定められているルールであり、どんな理由があっても延長することはできません。
例えば、今が2025年8月だとすれば、2015年8月以降の免除・猶予期間分が追納の対象となります。
2015年7月以前の期間については、残念ながら追納することは不可能です。
このため、「いつか余裕ができたら払おう」と考えていると、気づいた時には古い期間から順に追納の権利を失ってしまう可能性があります。
将来のために追納を考えているのであれば、この10年という期限を常に意識しておくことが大切です。
期限を過ぎたらどうなる?
では、10年の期限を過ぎてしまった免除・猶予期間は、一体どうなるのでしょうか。
結論から言うと、その期間の保険料を後から支払う手段はなくなります。
つまり、その期間分は将来の老齢基礎年金の計算に算入されず、年金額が満額よりも少ない状態で確定してしまいます。
これは、将来にわたって受け取る年金額が減額されることを意味します。
ただし、誤解してはいけないのは、年金が全くもらえなくなるわけではないという点です。
免除・猶予期間は、年金を受け取るために最低限必要な「受給資格期間(原則10年以上)」にはカウントされます。
そのため、受給資格期間を満たしていれば年金自体は受け取れます。
しかし、受け取れる「金額」が少なくなってしまうのです。
10年という期限は、将来の年金額を増やすチャンスのタイムリミットであると理解しておきましょう。
支払える順番(古い月から充当)
追納を行う際には、もう一つ知っておくべき大切なルールがあります。
それは、自分で支払う月を選ぶことができず、「最も古い期間の分から順に支払わなければならない」という決まりです。
例えば、5年前と3年前に免除期間があったとして、「先に3年前の分だけ支払いたい」ということはできません。
必ず、5年前の最も古い月の分から順番に納付していくことになります。
これは、10年の時効が迫っている古い期間から確実に納付できるようにするための仕組みです。
そのため、追納を申し込むと、現在追納可能な最も古い期間からの納付書が送られてきます。
もし、手元資金の都合で一部の期間だけ追納したい場合でも、この「古い順」という原則は変わりません。
どの期間から支払うことになるのか、事前に年金事務所などで確認しておくと計画が立てやすいでしょう。
支払い再開と追納の違い
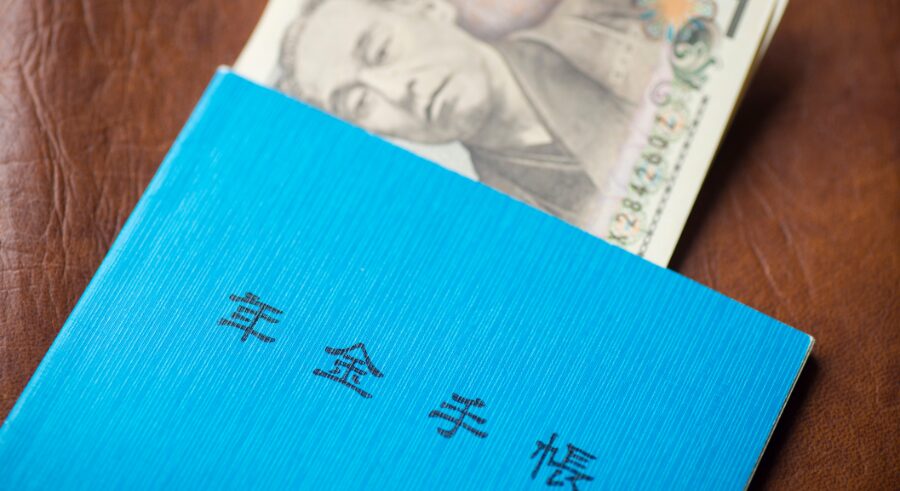
「今月分から払う」=再開
免除や猶予の期間が終わった後、まず行うべきことは保険料の「支払い再開」です。
これは、過去の分ではなく、「今月分」や「これから発生する分」の国民年金保険料を納めることを指します。
例えば、失業して免除を受けていた人が再就職し、厚生年金に加入した場合は、給与から天引きされる形で自動的に支払いが再開されます。
自営業者やフリーランスの方が、収入が安定したために免除申請をやめて、再び自分で保険料を納め始めるのも「再開」にあたります。
この支払い再開は、将来の未納期間を増やさないための基本中の基本です。
過去の分をどうするかを考える前に、まずは現在の義務をきちんと果たすことが大切になります。
支払い再開の手続きをしないままでいると、単なる「未納」期間が発生してしまい、将来の年金に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
「過去分を払う」=追納
一方で「追納」は、前述の通り、過去にさかのぼって保険料を支払う行為を指します。
対象となるのは、あくまで正式に免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けていた期間です。
現在の保険料を支払う「再開」とは、時間軸が全く異なります。
追納は義務ではありません。
これは、将来受け取る年金額を増額させるために、任意で行うプラスアルファの選択肢です。
現在の支払いを再開した上で、さらに経済的な余裕が生まれたときに、過去の空白期間を埋めるために利用するのが追納制度の一般的な活用法です。
「再開」は未来に向かっての支払い、「追納」は過去を清算するための支払い、と考えると分かりやすいかもしれません。
この二つは全く別の手続きであり、目的も異なることを理解しておくことが重要です。
選び方の判断基準
では、「支払い再開」と「追納」を、どのように考え、選んでいけば良いのでしょうか。
判断基準は非常にシンプルです。
まず最優先すべきは、現在の保険料を支払う「再開」です。
将来の未納を防ぎ、年金の受給資格を確実に維持することが何よりも大切だからです。
その上で、現在の家計に余裕があるかどうかを冷静に判断します。
もし、貯蓄に回せるお金があったり、ボーナスなどでまとまった収入があったりする場合には、「追納」を検討するタイミングと言えるでしょう。
追納のメリットは将来の年金額アップですが、現在の生活を圧迫してまで行うべきではありません。
まずは、現在の支払いをきちんと軌道に乗せること。
そして、無理のない範囲で、将来の自分への仕送りとして追納を活用するというのが、賢明な判断基準となります。
焦らず、ご自身のライフプランと照らし合わせて検討することが重要です。
追納額はどう計算される?延滞金の考え方

基本額と加算額(延滞金)
追納する保険料の額は、必ずしも免除を受けていた当時の金額と同じとは限りません。
追納額は、当時の保険料である「基本額」に、経過期間に応じた「加算額」が上乗せされる場合があります。
この加算額は、物価や賃金の変動を考慮して、追納する人と現役で納付している人との間の公平性を保つために設けられているものです。
いわゆる延滞金や利息のような性格を持つと考えると分かりやすいでしょう。
ただし、この加算額はいつでも発生するわけではありません。
免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合にのみ加算されます。
つまり、免除を受けてから2年以内に追納すれば、加算額は発生せず、当時の保険料額だけで済むのです。
この仕組みを理解しておくと、より有利なタイミングで追納計画を立てることができます。
延滞金が高くなる時期(免除から3年経過後など)
前述の通り、追納額に加算額、つまり延滞金のようなものが上乗せされるのは、免除・猶予期間の翌年度から数えて3年度目以降です。
これは、追納を先延ばしにするほど、支払う総額が増えてしまう可能性があることを意味します。
加算額の計算は、経過年数に応じて定められた率を乗じて行われるため、一般的に古い期間の分ほど加算額は大きくなる傾向にあります。
例えば、10年前に免除された保険料を追納する場合と、3年前に免除された保険料を追納する場合とでは、同じ1ヶ月分でも支払う総額は10年前の分の方が高くなります。
もし追納を検討しているのであれば、できるだけ早めに行動を起こす方が、経済的な負担を抑えることにつながります。
「いつか払おう」と後回しにしていると、本来払わなくてもよかったはずの加算額が増えてしまうことを覚えておきましょう。
追納額の確認方法(年金事務所・ねんきんネット)
「じゃあ、自分が追納する場合、具体的にいくらになるの?」と気になりますよね。
正確な追納額を確認するには、いくつかの方法があります。
最も手軽なのは、日本年金機構のオンラインサービス「ねんきんネット」を利用する方法です。
ねんきんネットに登録すれば、パソコンやスマートフォンから24時間いつでもご自身の年金記録を確認でき、追納可能な期間や金額のシミュレーションも行えます。
また、より詳しく相談したい場合は、お近くの年金事務所の窓口へ行くのが確実です。
年金手帳や基礎年金番号通知書、本人確認書類を持参すれば、担当者が追納可能な全期間の保険料額と加算額を具体的に算出してくれます。
電話での問い合わせも可能です。
追納を具体的に検討し始めたら、まずはこれらの方法で正確な金額を把握し、無理のない支払い計画を立てることが重要です。
追納と所得控除(税金メリット)

社会保険料控除の対象になる
追納制度を利用する上で、見逃せない大きなメリットが税金の軽減効果です。
追納によって支払った国民年金保険料は、その全額が「社会保険料控除」の対象となります。
これは、所得税や住民税を計算する際に、年間の総所得から支払った保険料の分を差し引くことができる制度です。
例えば、年間に30万円の追納をした場合、課税対象となる所得が30万円少なくなる、ということです。
この控除は、追納した本人分だけでなく、生計を一つにする家族の分の保険料を支払った場合にも適用されます。
例えば、夫が妻の過去の免除期間分を追納した場合、その支払額は夫の社会保険料控除の対象にできます。
将来の年金を増やすだけでなく、現在の税負担を軽くする効果もあるため、追納は二重にお得な制度と言えるかもしれません。
年末調整・確定申告での申請方法
社会保険料控除のメリットを受けるためには、ご自身で手続きを行う必要があります。
会社員や公務員の方であれば、勤務先で行われる「年末調整」の際に申請します。
毎年秋ごろに配布される「給与所得者の保険料控除申告書」という書類に、その年に支払った追納額を記入し、支払いを証明する書類を添付して提出します。
一方で、自営業者やフリーランス、年金生活者の方などは、翌年の2月から3月にかけて行う「確定申告」で手続きをします。
確定申告書の「社会保険料控除」の欄に支払額を記入し、同様に証明書類を添えて税務署に提出します。
この際に必要となる証明書類は、日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」です。
通常、11月上旬ごろに郵送されてくるので、なくさないように大切に保管しておきましょう。
所得税・住民税の軽減効果
社会保険料控除を申請することで、具体的にどのくらい税金が軽減されるのでしょうか。
軽減される金額は、その人の所得税率によって異なります。
所得税は累進課税といって、所得が高い人ほど高い税率が適用される仕組みです。
例えば、所得税率が10%の人が20万円の追納をした場合、単純計算で所得税が2万円(20万円×10%)軽減されます。
さらに、住民税の税率は多くの場合、一律10%程度ですので、同じく2万円(20万円×10%)ほど安くなる計算です。
このケースでは、合計で約4万円の税負担が軽くなることになります。
所得税率が20%の人であれば、所得税だけで4万円の軽減となり、その効果はさらに大きくなります。
追納を検討する際は、この税金の還付・軽減額も考慮に入れると、実質的な負担額をより正確に把握することができるでしょう。
追納のメリット・デメリット

将来の年金額アップ
追納制度を利用する最大のメリットは、何と言っても将来受け取る老齢基礎年金の金額が増えることです。
国民年金の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付した場合に、満額を受け取ることができます。
免除や猶予を受けた期間がある場合、その月数分だけ年金額は減額されてしまいます。
追納をすることで、この減額分を取り戻し、満額に近づけることが可能です。
これは、生涯にわたって受け取る年金の総額が増えることを意味します。
例えば、1年分(12ヶ月)の保険料を追納すれば、年間の年金受給額が約2万円増額されます(令和6年度の満額で計算した場合)。
これが10年、20年と続けば大きな金額になります。
低金利が続く現代において、将来の自分への確実な仕送りとして、これほど有利な選択肢は少ないかもしれません。
延滞金が発生する可能性
一方で、追納のデメリットとして考えなければならないのが、加算金の存在です。
前述の通り、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加えて経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
これは、実質的な延滞金と考えることができます。
特に、10年近く前の古い期間の分を追納しようとすると、この加算額が思ったよりも高額になることがあります。
そのため、追納する総額が、本来支払うはずだった保険料よりもかなり多くなってしまう可能性があるのです。
この加算額の存在を知らずに追納を考えると、後から「こんなに高いとは思わなかった」と感じるかもしれません。
追納を検討する際には、必ず事前に年金事務所や「ねんきんネット」で正確な支払総額を確認し、その金額を支払う価値があるかを冷静に判断する必要があります。
一度支払うと取り消しできないリスク
追納を考える上で、非常に重要な注意点があります。
それは、「一度納付した追納保険料は、いかなる理由があっても返還されない」というルールです。
例えば、追納をした後に急にお金が必要になったからといって、「やっぱり追納をやめて、支払ったお金を返してほしい」ということは一切できません。
また、「追納額を間違えて多く払いすぎてしまった」といったケースでも、取り消しや返金は認められません。
追納は、将来の年金を増やすための確定的な支払いとなります。
そのため、追納を行う前には、ご自身の家計状況や将来のライフプランを慎重に検討する必要があります。
現在の生活を圧迫しないか、本当に今支払うべきなのかをよく考え、後悔のないように意思決定をすることが何よりも大切です。
追納しない場合の将来への影響

年金額の減少(例:1年未納で年間〇円減額)
もし追納をしないという選択をした場合、どのような影響があるのでしょうか。
最も直接的な影響は、将来受け取る老齢基礎年金の金額が、免除・猶予を受けた期間分だけ減額されることです。
国民年金は40年(480ヶ月)の加入で満額が支給される仕組みです。
仮に令和6年度の満額年金額(年額816,000円)を基準に考えると、1ヶ月分の未納があるだけで、年間の受給額は約1,700円(816,000円 ÷ 480ヶ月)少なくなります。
もし1年間(12ヶ月)追納しない期間があれば、将来受け取る年金額は毎年約20,400円(1,700円 × 12ヶ月)も減ってしまう計算です。
これが5年分となれば、年間で10万円以上の差になります。
この減額は生涯にわたって続くため、長生きすればするほど、追納した場合との受給総額の差はどんどん開いていくことになります。
追納しないという選択は、この将来の減額を受け入れるということなのです。
受給資格期間への影響(免除期間は資格に含まれるが額は減る)
年金額が減る一方で、知っておくと少し安心できる点もあります。
それは、年金を受け取るために最低限必要な「受給資格期間」への影響です。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や免除された期間などを合計して、原則10年(120ヶ月)以上ないと受け取ることができません。
ここで重要なのは、保険料の支払いを「免除」または「猶予」された期間は、この受給資格期間に算入されるという点です。
そのため、免除期間があるからといって、直ちに年金を受け取る権利そのものがなくなるわけではありません。
例えば、保険料を納付した期間が8年しかなくても、免除期間が2年あれば、合計で10年の受給資格期間を満たすことができます。
繰り返しますが、これはあくまで「年金を受け取る権利」の話です。
実際に受け取れる「年金額」の計算においては、免除期間は保険料を納めていない期間として扱われるため、その分、金額が少なくなるという事実は変わりません。
部分的な追納はできる?

一部期間だけの追納が可能
追納を検討する際に、「免除期間が全部で5年あるけれど、一括で支払うのは難しい」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
追納は、必ずしも対象期間のすべてを一度に行う必要はありません。
「一部の期間だけ」を追納することも可能です。
例えば、追納可能な期間が60ヶ月分あったとして、まずは経済的な負担が少ない12ヶ月分だけを追納するといった柔軟な対応ができます。
追納の申し込みをすると、日本年金機構から納付書が送られてきますが、その納付書を使って一部だけを支払うことも、年金事務所に相談すれば可能です。
これにより、ご自身の家計の状況に合わせて、無理のない範囲で計画的に追納を進めていくことができます。
まとまった資金がなくても、少しずつ将来の年金を増やしていけるのは、この制度の大きな利点と言えるでしょう。
効率的に追納する順番(延滞金の高い期間から)
部分的に追納を進める場合、どのように支払っていくのが効率的でしょうか。
追納には「最も古い月の分から順に支払う」という原則があります。
一方で、加算額(延滞金)は、古い期間の分ほど高くなる傾向があります。
この二つのルールを考えると、基本的には時効が迫っていて、かつ加算額が高くなりがちな古い期間から優先的に納付していくのが合理的です。
例えば、10年分の追納可能期間がある場合、まずは1年分だけ追納して、最も古い1年分を解消するといった形です。
これにより、加算額がこれ以上増えるのを防ぎつつ、時効による権利の消滅も回避できます。
ただし、どの期間をどのように支払うのが最も得策かは、個々の状況によって異なります。
ご自身の追納可能な期間とそれぞれの加算額を年金事務所で確認し、どのくらいの期間を追納したいのかを伝えて相談するのが一番確実で効率的な方法と言えるでしょう。
追納に向いている人・向いていない人

将来の受給額を増やしたい人
追納制度の利用が特に向いているのは、やはり「将来受け取る年金額を1円でも多くしたい」と強く考えている人です。
老齢基礎年金は、一度受け取り始めると生涯にわたって支給される終身保障です。
そのため、追納によって年金額を少しでも増やしておくことは、長生きした場合の経済的な安心に直結します。
特に、自営業者やフリーランスの方で、厚生年金のような上乗せ部分がない国民年金第1号被保険者にとっては、老後の生活を支える基礎年金の額を最大化しておくことの重要性は非常に高いと言えます。
現在の生活に一定の余裕があり、将来への投資としてコツコツと資産を積み立てていきたいと考えている方にとって、追納は非常に堅実で有効な選択肢となるでしょう。
現在の収入や税制メリットを活用できる人
追納は、現在の収入が安定しており、経済的に余裕のある人にも向いています。
特に、追納によって支払った保険料が全額「社会保険料控除」の対象になるという税制メリットを最大限に活用できる方にはおすすめです。
所得税は所得が高いほど税率も高くなるため、所得が高い年に追納を行えば、それだけ税金の軽減効果も大きくなります。
例えば、一時的に収入が増えた年や、退職金を受け取った年などにまとめて追納を行うと、大きな節税につながる可能性があります。
このように、将来の年金額を増やすという目的だけでなく、現在の税負担を軽減するという視点からも追納を捉えることができる人にとって、この制度は非常に魅力的に映るはずです。
ご自身の収入状況と税率を確認し、最も効果的なタイミングで追納を計画するのも賢い方法です。
無理な支払いで生活が圧迫される人は注意
一方で、追納を慎重に考えるべき人もいます。
それは、現在の収入で日々の生活を送るのが精一杯で、貯蓄に回す余裕があまりない人です。
追納はあくまで任意であり、義務ではありません。
将来の年金額を増やしたいという気持ちは大切ですが、そのために現在の生活を切り詰めすぎたり、借入れをしてまで追納したりするのは本末転倒です。
無理な支払いは家計を圧迫し、精神的なストレスにもつながりかねません。
また、一度支払った追納保険料は返還されないため、急な出費が必要になった際に対応できなくなるリスクもあります。
まずは、日々の生活を安定させ、現在の保険料をきちんと納付することを最優先に考えるべきです。
追納は、あくまで生活に余裕が生まれてから検討する、というスタンスでいることが大切です。
追納の手続きの流れ
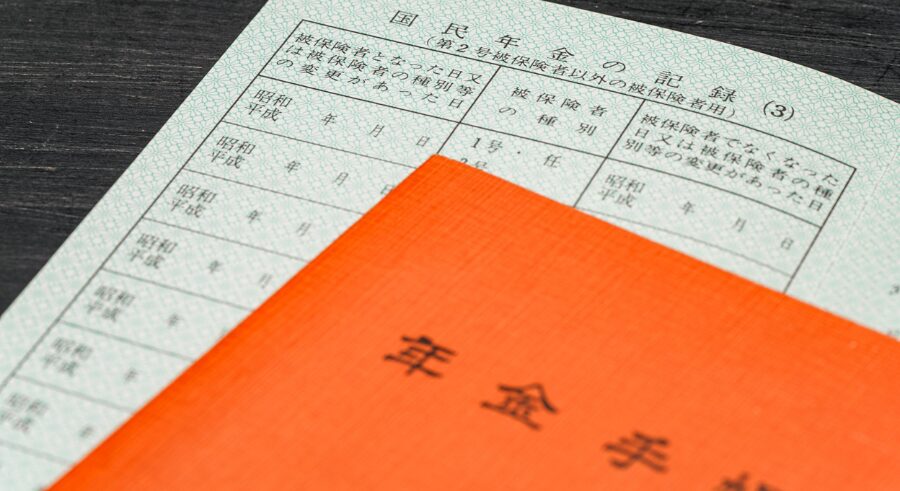
年金事務所での申請手順
追納をしたいと決めたら、まずは手続きの第一歩として申請を行う必要があります。
申請先は、ご自身の住所地を管轄する「年金事務所」です。
事務所の窓口へ直接出向いて申請する方法のほか、郵送で手続きを行うことも可能です。
窓口に行く場合は、担当者に追納したい旨を伝えれば、必要な「国民年金保険料追納申込書」を渡してくれ、記入方法についても案内してもらえます。
その場で不明点などを直接質問できるのが窓口申請のメリットです。
郵送の場合は、日本年金機構のホームページから申込書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上、管轄の年金事務所へ送付します。
どちらの方法でも手続きは可能なので、ご自身の都合の良い方を選ぶと良いでしょう。
申請自体はそれほど難しいものではありません。
必要書類
追納の申し込み手続きには、いくつかの書類が必要になります。
まず必須なのが「国民年金保険料追納申込書」です。
これは年金事務所の窓口でもらうか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
申込書を記入する際には、ご自身の基礎年金番号が必要になります。
基礎年金番号は、年金手帳や基礎年金番号通知書、ねんきん定期便などで確認できますので、事前に準備しておくとスムーズです。
もし番号がわからない場合は、年金事務所で調べてもらうこともできます。
窓口で手続きをする場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類も持参しましょう。
代理人が手続きを行う場合は、委任状や代理人の身分証明書なども必要になります。
事前に管轄の年金事務所に必要なものを問い合わせておくと、二度手間を防ぐことができます。
納付書の受け取りから支払いまでの流れ
「国民年金保険料追納申込書」を提出してから、およそ1ヶ月ほどで、日本年金機構から追納専用の「納付書」が郵送で届きます。
この納付書には、追納する期間と金額が印字されています。
内容に間違いがないかを確認しましょう。
納付書が手元に届いたら、それを使って保険料を支払います。
支払いができる場所は、銀行や郵便局、信用金庫などの金融機関の窓口です。
また、一部のコンビニエンスストアでも支払いが可能です。
納付書に記載されている納付期限までに支払いを済ませましょう。
支払いが完了すると、領収書が渡されます。
この領収書は、年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける際に、支払いを証明する大切な書類となりますので、絶対に紛失しないよう大切に保管しておいてください。
これで追納の一連の手続きは完了です。
実例紹介:追納を行ったケース

30代会社員Aさんの例(支払額・将来受給額の変化)
ここで、実際に追納を行った方の例を見てみましょう。
30代の会社員Aさんは、学生時代に「学生納付特例」を利用していた2年間(24ヶ月)分の保険料が未納のままでした。
現在の収入に余裕ができたため、将来のために追納を決意しました。
Aさんが追納を申し込んだところ、当時の保険料に少し加算額がつき、24ヶ月分の追納額の合計は約40万円でした。
この約40万円を支払ったことで、Aさんの将来の老齢基礎年金は、年間で約4万円増額されることになりました。
もしAさんが65歳から85歳までの20年間年金を受け取ると仮定すると、総額で約80万円(4万円×20年)も多く受け取れる計算になります。
支払った40万円が、将来倍になって返ってくるようなイメージです。
さらに、Aさんは追納した年の年末調整で社会保険料控除を申請し、所得税と住民税が合わせて数万円軽減されました。
本人の感想と注意点
追納を終えたAさんは、次のように話してくれました。
「手続きは年金事務所に電話で問い合わせて、申込書を郵送で取り寄せたので、思ったよりも簡単でした。
一番のメリットは、やはり将来もらえる年金が増えるという安心感です。
これで老後の不安が少し和らぎました。
また、年末調整で税金が戻ってきたのも嬉しかったです。
ただ、注意点としては、やはり約40万円というまとまった出費になったことです。
私はボーナスを見越して計画的に準備しましたが、いきなり支払うのは大変だと感じました。
事前に自分の追納額がいくらになるのかをしっかり確認し、無理のない資金計画を立てることが何よりも大切だと思います。
また、どの期間を追納できるのか、10年の期限があることも知っておくべきでした。」
Aさんの体験談は、追納を検討する上で非常に参考になりますね。
まとめ
今回は、国民年金の追納制度について、その仕組みからメリット・デメリット、具体的な手続きまでを解説しました。
この記事のポイントを改めて整理してみましょう。
追納は、免除や猶予を受けた期間の保険料を後から支払うことで、将来の年金額を満額に近づけるための制度です。
追納できるのは承認を受けてから10年以内の期間で、古い月の分から順に支払うルールがあります。
大きなメリットは、将来の年金額が増えることと、支払った全額が社会保険料控除の対象となり税金が安くなる点です。
一方で、3年度目以降は加算金が発生することや、一度支払うと取り消せない点には注意が必要です。
追納は義務ではありません。
現在の生活を大切にしながら、ご自身の経済状況やライフプランに合わせて、将来への投資として活用できるかを慎重に判断することが重要です。
もし少しでも疑問や不安な点があれば、一人で悩まずに「ねんきんネット」で情報を確認したり、お近くの年金事務所に相談したりしてみてください。
あなたの明るい未来のために、最適な選択ができることを願っています。