\今話題の商品をランキングでチェック/
婚姻届はひとりで提出できる?割合と手続き・必要書類を徹底解説
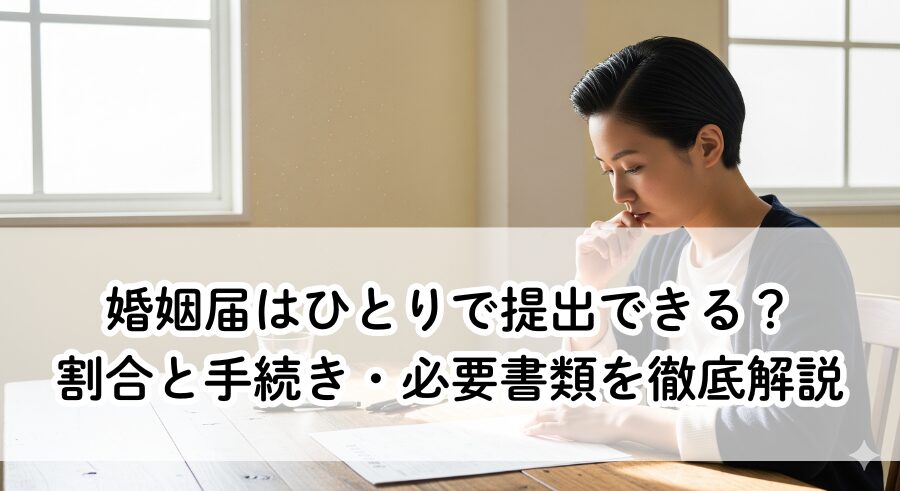
婚姻届はひとりで提出できる?割合と手続き・必要書類を徹底解説
結婚という人生の大きな節目において、法的な手続きの中心となるのが「婚姻届」の提出です。
多くのカップルが「ふたりで一緒に提出したい」と考える一方で、仕事の都合や遠距離など、様々な事情から「ひとり」で提出せざるを得ない、あるいはその方が効率的だと考えるケースも少なくありません。
この記事では、「婚姻届をひとりで出す」という選択肢について、その実態から具体的な手続き、必要書類、そして後悔しないための注意点まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。
ひとりで提出することに不安を感じている方、手続きをスムーズに進めたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みいただき、自信を持って新たな一歩を踏み出すための準備を整えてください。
婚姻届をひとりで出す人の割合は?気になる実態と理由

「婚姻届をひとりで提出する人は、一体どれくらいの割合いるのだろう?」――この疑問は、ひとりで役所へ向かうことを検討している多くの方が抱くものです。
この問いの背景には、単なる統計への興味だけでなく、「自分の状況は一般的なのか」「ひとりで提出しても問題ないのか」という、一種の社会的な確認を求める心理が隠されています。
結論から言うと、婚姻届をどちらか一方が単独で提出する割合に関する、国や自治体による公式な統計データは存在しません。しかし、法的には全く問題なく、実際には多くのカップルがこの方法を選択しています。
検索される「割合」というキーワードは、数字そのものよりも「それが普通のことである」という安心材料、つまり社会的証明を求めていることの表れと言えるでしょう。
では、なぜ多くのカップルがひとりで提出するという選択をするのでしょうか。
その理由は、現代の多様なライフスタイルに根差しています。
- 仕事の都合によるスケジュールの不一致:
最も一般的な理由の一つです。お互いの勤務形態が異なったり、繁忙期で休みが取れなかったりと、平日の日中にふたりで役所の窓口へ行く時間を確保するのが難しいカップルは少なくありません。 - 地理的な距離:
結婚を機に同居を始めるカップルなど、婚姻届を提出する時点ではまだ別々の場所に住んでいるケースです。
どちらか一方が、新居の所在地や自身の本籍地の役所に提出する方が効率的です。 - 手続きの効率化:
役所に近い方や、行政手続きに慣れている方が代表して提出する方がスムーズに進むという、合理的な判断です。 - 価値観の多様化:
婚姻届の「提出」という行為そのものに、必ずしもふたりでいることのセレモニー的な価値を置かないカップルも増えています。
提出はあくまで法的な手続きと捉え、その後の食事会や記念旅行など、別の形で結婚を祝うことを重視する考え方です。
近年、特に40代以上の中高年層においては、法的な形式に縛られないパートナーシップを望む傾向も見られます。
ある調査では、40〜80代の男女のうち約6割が「婚姻届は出さない・別居の恋人関係」を希望するという結果も出ており 、結婚という制度に対する価値観そのものが多様化していることがわかります。
このような社会的な変化を背景に考えれば、婚姻届の提出方法が個々のカップルの事情や価値観に合わせて柔軟になっているのは、ごく自然な流れと言えるでしょう。
ひとりで婚姻届を提出する完全ガイド【準備から提出まで】

婚姻届をひとりで提出することは、法的に認められた正当な手続きです。
しかし、パートナーがその場にいない分、不備があった際のリスクは高まります。
ここでは、準備から提出までの全ステップを網羅した完全ガイドとして、失敗なくスムーズに手続きを完了させるための要点を解説します。
Step 1: 婚姻届の入手と準備
まず、手続きの土台となる婚姻届用紙を手に入れるところから始めます。
- 入手場所:
婚姻届の用紙は、全国どこの市区町村役場の戸籍担当窓口でもらうことができます 。用紙の様式は全国共通のため、提出先の役所でもらう必要はありません。 - 予備の確保:
記入ミスは誰にでも起こり得ます。書き損じに備えて、必ず2〜3枚は余分にもらっておきましょう 。
- デザイン婚姻届の利用:
最近では、自治体オリジナルの「ご当地婚姻届」や、キャラクターがデザインされたもの、インターネットでダウンロードできるものなど、デザイン性の高い婚姻届も人気です 。ただし、ダウンロードして使用する場合は、必ず A3サイズで印刷する必要がある点に注意してください。規定外のサイズでは受理されません。 - 提出前の事前チェック:
ひとりで提出する場合に最も推奨されるのが、提出予定日より前に、完成した婚姻届を役所の窓口でチェックしてもらう「事前確認」です 。これにより、当日になって発覚する記入ミスや書類不備を未然に防ぐことができ、安心して提出日を迎えられます。
Step 2: 提出に必要なものチェックリスト
ひとりで提出する際に持参すべきものを、その目的と注意点と共にリストアップしました。特に「推奨」とされているものは、手続きを円滑に進めるための重要な鍵となります。
| 項目 | 必要度 | 目的と注意点 |
| 記入済みの婚姻届 | 必須 | 法的効力を発生させるための本体書類。 届出人であるふたりと、証人2名の署名が漏れなく記入されていることを確認してください。 |
| 提出者の本人確認書類 | 必須 | 窓口に来た人の身元を確認するために必要です。 パートナーの分は不要です 。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きのものであれば1点、健康保険証や年金手帳など顔写真がないものでは2点の提示が求められます 。 |
| 二人の旧姓印鑑 | 強く推奨 | 記入ミスがあった場合の訂正に実質的に必須です。 2021年の法改正で届書への押印は任意になりましたが 、訂正には押印(または署名)が必要です。ひとりで提出する場合、パートナーの記入箇所にミスがあっても、その方の印鑑がなければその場で訂正できず、持ち帰ることになります 。このリスクを避けるため、必ずふたり分の旧姓印鑑を持参しましょう。 |
| 戸籍謄本(の情報) | 参考 | 本籍地を正確に記入するために役立ちます。 2024年3月1日から、法改正により婚姻届提出時の戸籍謄本の添付は原則不要となりました 。しかし、これは手続き上の大きな変化であり、新たな注意点を生んでいます。以前は戸籍謄本を取得する過程で、自身の正確な本籍地や氏名を確認できましたが、その機会がなくなったことで、記憶違いによる記入ミスが増える可能性があります。特に本籍地の表記は「〇〇番地」なのか「〇〇番」なのかなど、一字一句正確でなければなりません。このミスを防ぐため、提出は不要でも、事前に戸籍謄本を取得して正確な情報を手元に用意しておくことを強くお勧めします。 |
Step 3: 役所での提出手順と時間外受付
書類の準備が整ったら、いよいよ提出です。提出場所と時間に関するルールを正確に理解しておきましょう。
- 提出場所:
婚姻届は、「夫または妻の本籍地」あるいは「夫または妻の所在地(住所地)」のいずれかの市区町村役場で提出できます 。
「所在地」には、旅行先など一時的な滞在地も含まれますが、手続きが複雑になる可能性があるため、基本的には本籍地か住所地の役所を選ぶのが一般的です。 - 提出プロセス:
役所の開庁時間内に戸籍担当窓口へ行き、準備した書類一式を提出します。
職員がその場で内容を確認し、不備がなければ受理され、その「受理された日」が正式な婚姻成立日となります。 - 時間外・休日受付:
多くの役所では、夜間や土日祝日でも「時間外受付窓口(夜間休日窓口)」で婚姻届を預かってもらえます 。
これにより、ふたりの記念日など、特定の日に提出することが可能です。
ただし、これには大きな注意点があります。
時間外窓口では、警備員や当直職員が書類を「預かる」だけで、内容の正式な審査は翌開庁日に行われます。
もし、その審査で訂正不可能な不備(例:証人の署名漏れ、訂正に必要な印鑑がない等)が見つかった場合、届出は受理されず、提出日に遡って婚姻を成立させることはできません。
婚姻成立日がずれてしまうリスクを避けるためには、やはり事前の書類チェックが極めて重要になります。
証人欄の記入は必須!誰に頼む?注意点を解説

婚姻届が法的に有効となるためには、届出人であるふたりの署名に加え、成人の証人2名による署名が不可欠です 。
この証人の項目は、手続きの中で多くの人が疑問に思うポイントであり、また人間関係が関わる重要なステップでもあります。
- 証人になれる人:
証人は、18歳以上であれば、国籍や届出人との関係性を問わず誰でもなることができます。
最も一般的には、お互いの父親にお願いするケースが多く、約8割のカップルが親に依頼しているというデータもあります 。
もちろん、母親や兄弟姉妹、お世話になった恩師、親しい友人など、ふたりが信頼する人であれば問題ありません。 - 依頼する際のマナー:
証人をお願いすることは、ふたりの結婚を公に認めてもらう最初のステップであり、相手にとっては名誉なことです。
依頼する際は、可能な限り直接会ってお願いし、結婚の報告と共にその理由を丁寧に伝えましょう。
遠方に住んでいる場合は、電話で誠意を伝えた上で、婚姻届を郵送するなどの方法を取ります。 - 証人欄の記入内容:
証人には、婚姻届の証人欄に自筆で以下の項目を記入してもらう必要があります 。- 氏名
- 生年月日
- 住所(住民票に記載の通り)
- 本籍地
- 注意すべき点:
証人に関する最も多いトラブルは、記入内容の誤りです。
特に「本籍地」は、現住所と異なる場合が多く、正確に覚えていない方もいます。
証人にお願いする際には、可能であれば本籍地が確認できるもの(運転免許証など)を見ながら記入してもらうと安心です。
また、感謝の気持ちを込めて、後日改めてお礼の品を贈ったり、食事に招待したりすると、より良い関係を築くことができるでしょう。
この証人選びと依頼のプロセスは、単なる事務手続きではなく、ふたりの門出を大切な人たちと分かち合う最初の機会です。
このステップを丁寧に行うことで、婚姻届という一枚の紙が、より一層思い出深いものになります。
ひとりで婚姻届を出すメリット・デメリットとトラブル回避策

ひとりで婚姻届を提出するという選択は、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや潜在的なリスクも伴います。
これらを事前に理解し、対策を講じることで、後悔のない選択が可能になります。
メリット (Advantages)
- 柔軟性と効率性:
最大のメリットは、時間的な制約から解放されることです。ふたりのスケジュールを無理に合わせる必要がなく、どちらか一方の都合の良いタイミングで手続きを完了できるため、多忙なカップルにとっては非常に合理的です。 - 精神的な負担の軽減:
行政手続きが苦手なパートナーがいる場合、得意な方が代表して行うことで、全体のストレスを軽減できます。 - 記念日の重視:
提出という行為よりも、その後のディナーや旅行といった「お祝い」の時間を大切にしたいカップルにとって、事務手続きを効率的に済ませることは、より充実した記念日を過ごすための賢明な選択と言えます。
デメリットと後悔の可能性 (Disadvantages and Potential for Regret)
- 共有体験の喪失:
「役所の前でふたりで記念撮影をしたかった」「夫婦になった瞬間を一緒に味わいたかった」など、後から振り返って、特別な瞬間を共有できなかったことに寂しさを感じる可能性があります。 - 参加意識の不均衡:
事前の話し合いが不十分だと、提出に行かなかった側が「自分だけが関与できなかった」と疎外感を抱くことがあります。 - 手続き上のリスク:
最も現実的なデメリットは、書類に不備があった際の対応の困難さです。
特に、その場にいないパートナーの記入箇所に訂正が必要な場合、代理で訂正することはできません 。
これにより、婚姻届が受理されず、希望していた記念日に婚姻を成立させられないという最悪の事態も起こり得ます 。
トラブル回避策 (Trouble-Avoidance Strategies)
これらのデメリットやリスクは、適切な準備によって回避、あるいは軽減することが可能です。
重要なのは、手続き上のトラブルと感情的な後悔の両方に対処することです。
- 印鑑によるリスク管理: 手続き上の最大のリスクである「訂正不可」の問題は、ふたり分の旧姓印鑑を持参することでほぼ解決できます。
これにより、万が一ミスが発覚しても、その場で適切に訂正することが可能になります。 - 事前確認の徹底: 役所の窓口での事前チェックは、書類の完璧さを保証する最も確実な方法です。これにより、当日の不安を完全に取り除くことができます。
- 新たな思い出の創造: 「共有体験の喪失」という感情的なデメリットに対しては、意識的に代わりのセレモニーを計画することが有効です。
例えば、提出した側が受理された婚姻届や役所の建物の写真を撮ってすぐに共有し、その日の夜にふたりで豪華なディナーを楽しむ、あるいは週末に改めて記念の場所へ出かけるなど、ふたりらしい祝い方を計画しましょう。
手続きの効率化と、思い出作りの両立は十分に可能です。
後悔しないためのパートナーとの話し合いと心構え

婚姻届をひとりで提出するという決断は、単なる手続き上の選択ではありません。
それは、ふたりのパートナーシップのあり方を映し出す、最初の共同作業の一つです。
このプロセスを円滑に進め、後悔を残さないためには、技術的な準備以上に、パートナーとの丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
- オープンな話し合い:
なぜひとりで提出するのか、その理由とメリット・デメリットについて、ふたりで率直に話し合いましょう。
「仕事が忙しいから」という理由であっても、それを一方的に決定するのではなく、「今回はこういう理由で、私が代表して提出しようと思うけど、どうかな?」と相手の意向を確認することが重要です。
このプロセスを通じて、双方が納得した上での共同決定であることが確認できます。 - 役割分担の明確化:
ひとりが提出役を担うのであれば、もう一方は書類の準備や証人へのお願いを担当するなど、役割を分担することで、双方が手続きに主体的に関わっているという意識を持つことができます。 - 当日のプランを共有:
提出当日の流れを事前に共有しておくことも大切です。
「何時頃に役所に行く予定か」「無事に受理されたら、すぐに電話で報告するね」といった小さな約束事が、その場にいないパートナーの不安を和らげ、一体感を生み出します。 - 手続きをパートナーシップの土台に:
婚姻届の提出は、これからふたりで乗り越えていく数多くのライフイベントの序章に過ぎません。
住宅の契約、子育て、資産形成など、夫婦は常に協力して様々な手続きや決断を行っていきます。
この最初の行政手続きを、お互いを尊重し、効率的に協力し合うための良い練習機会と捉えましょう。
ここで築かれた信頼関係とコミュニケーションのスタイルは、間違いなくこれからの結婚生活の強固な土台となります。
婚姻届のひとりで提出に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、婚姻届をひとりで提出する際に特に多く寄せられる質問について、簡潔かつ明確に回答します。
- 代理人(友人や親)に提出をお願いできますか?
-
はい、可能です。婚姻届や離婚届などの戸籍届は、届出人本人(夫と妻)が署名したものであれば、代理人が窓口に持参することができます。
この場合、代理人は法律上「使者」という扱いになり、委任状は不要です 。ただし、窓口では使者自身の本人確認が行われるため、身分証明書が必要になります。
また、使者は一切の訂正作業ができないため、書類に完璧な状態であることが絶対条件となります。 - 提出時にパートナーの本人確認書類も必要ですか?
-
いいえ、不要です。本人確認は、あくまで窓口に来庁した方に対して行われます 。
そのため、提出者自身の本人確認書類だけを持参すれば問題ありません。
なお、不正な届出を防ぐため、来庁しなかった届出人(パートナー)には、後日、届出があったことを知らせる通知が役所から郵送されます 。 - 提出した日が「結婚記念日」になるのですか?
-
法律上、婚姻が成立するのは、役所が婚姻届を「受理した日(受理日)」です 。
開庁時間内に提出し、その場で不備なく受理されれば、その日が婚姻成立日(結婚記念日)となります。
夜間や休日に提出した場合、書類に不備がなければ、提出日に遡って受理されるため、その日が記念日になります。
しかし、もし訂正が必要な不備が見つかり、翌開庁日に修正した場合は、その修正が完了した日が受理日となるため、注意が必要です。 - 婚姻届の提出に戸籍謄本は不要になったと聞きましたが本当ですか?
-
はい、本当です。
2024年3月1日より、戸籍情報連携システムの本格運用が開始されたことに伴い、婚姻届を提出する際の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が、原則として不要になりました 。
これにより、本籍地以外の役所に提出する際の手間が大幅に軽減されました。
ただし、前述の通り、届書に本籍地を正確に記入する必要があるため、ご自身の正確な本籍地情報を事前に確認しておくことが非常に重要です。 - 婚姻届を提出したら、住所も自動で変わりますか?
-
いいえ、自動では変わりません。
婚姻届は「戸籍」に関する手続きであり、「住民票(住所)」の変更は別途行う必要があります 。
結婚に伴い住所を移す場合は、旧住所の役所で「転出届」を提出し、新住所の役所で「転入届」を提出する手続きが必要です。
同じ市区町村内で引っ越す場合は「転居届」を提出します。これらの手続きは、婚姻届の提出と同じ日に行うことも可能です。
まとめ
婚姻届をひとりで提出することは、現代の多様なライフスタイルにおいて、非常に合理的で一般的な選択肢です。
公式な割合のデータはありませんが、法的に何ら問題はなく、多くのカップルがそれぞれの事情に合わせてこの方法を選んでいます。
重要なのは、その選択がふたりの合意に基づいたものであること、そして、ひとりで提出するからこその注意点を理解し、万全の準備を整えることです。
- 書類の完璧な準備:
証人2名の署名を確実に得て、特に本籍地の表記など、すべての項目を正確に記入する。 - 訂正への備え:
万が一の記入ミスにその場で対応できるよう、ふたり分の旧姓印鑑を必ず持参する。 - 事前のコミュニケーション:
なぜひとりで提出するのか、どのように記念日を祝うのかを事前に話し合い、お互いの納得と安心感を確保する。
これらのポイントを押さえることで、手続き上のトラブルと感情的な後悔の両方を避け、スムーズに新しい門出を迎えることができます。
婚姻届の提出は、ふたりの人生が法的に一つになる神聖な手続きであると同時に、これから始まる共同生活の第一歩です。
ふたりにとって最も納得のいく形でこの日を迎え、素晴らしい結婚生活をスタートさせてください。